販売者に会いにゆく (旧・今月の人)
宮川清さん
若いもんに負けられないと思うから、自然と一所懸命になる
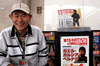
伸びた背筋に黒い髪からは想像しにくいが、宮川清さんは、1930年生まれの74歳。東京都内の販売者では最高齢だ。激しい雨の日と、京王多摩センター駅前への出張販売の日を除く毎日、新宿西口小田急デパートの前に立っている。
「売れない日や売れない時間帯をどこまで我慢できるか、自分との闘いなんですよ。つい最近も、朝の9時から昼の1時前まで3時間近く立っていて、あれだけ人通りがあるのに1冊も売れなかった。雨降りの日曜日だけど、さすがにこたえたね」
昨年12月、暮れの喧騒のなかでビッグイシューを売り始めた。路上生活に入ったきっかけは「家庭の不和」。そのあたりの事情は、お互いに言いたいことはあるはずだから、こっちの言い分がかりじゃ家族を傷つけることになる、と多くを語らない。
「こういう生活に入ったのは、昨年の9月頃からですから、ビッグイシューに行き合うまでの4ヶ月は収入がなくて、よく過ごしてこられたなと思います。所持金2000円は、1週間ももたなくて風呂にも入れない。最初は、何もわからずにビルのまわりの腰掛けで2日過ごしたけれど、警備員から寝そべっちゃだめだと言われて、地下通路で寝るようになって。周りの人から聞いて、炊き出しや道路の清掃ボランティアの後に出されるおにぎりで何とか食いつなぐようになったけれど、不安な毎日でした」
近くで寝起きしていた顔見知りからビッグイシューの話を聞いて心を決めた。元手の10冊はすぐに売れたが、「そのお金ですぐまた仕入に行けばいいのに、初めてのことだし、ホームレスとして人前に立つことに精神的に疲れてしまって、あくる日まで考えてまた仕入に行ったんですよ」。その後は、販売数を増やし、今や1日平均30冊を売り上げる。出張販売で知り合った会社社長から、パーティへ出張販売してほしいと言われ、運んでいったこともある。
「いちどきに100冊売ったのは販売記録になるんじゃないかな。でも、いつか1日通していつもの場所で100冊売ってみたいね。大げさかもわからんけど、私にとってビッグイシューは命の恩人みたいなもの。若いもんに負けられないと思うから、自然と一所懸命になるのかもしれませんよ。酒もギャンブルもやらないので、少しずつ余裕もできました」
「でもそのなかから仕入場所に缶コーヒーを買ってきて皆に配ってるんですよ」とビッグイシューのスタッフが小声で教えてくれた。話を聞いたのは、新宿の路上にある宮川さんの住まい。中には、ビッグイシューを売るようになってから揃えたという生活道具が整然と並んでいる。ろうそくの灯りの下で、宮川さんは、時折、足をさすっている。足の調子が悪いのだというが、足を揉むために数回小さい折り畳み椅子に座る以外は、1日中立ったままで売る。
「売る限りは、立って声をかけて売りますよ。40年近く建設現場で働いて、ビルの階段を上り下りしていましたし、戦争中の物のない時代も知っています。辛抱強く耐えることには慣れていますからね」
東京で生まれ、長屋暮らしをしていたが、10歳のときに父親が亡くなって、母親の親戚がいる田舎へ身を寄せた。「皇紀2600年」の提灯行列の年だった。翌1941年、太平洋戦争開戦。その後も同じ土地で暮らしていたが、1961年、31歳のとき東京で建築関係の内装の仕事に就いた。高度経済成長期、社員数人の下請け会社で、ビルの工事に次々と関わり、4年前まで足かけ40年同じ仕事を続けてきた。
「2回目の心筋梗塞の発作の後、職場を離れました。最近の建築現場は条件が厳しくなっていて。不景気な世の中だから病気した年寄りは、敬遠されちゃうんですよね」
宮川さんは、2回だけ、灯りを見つめたまま涙声になった。自分で手がけた日本で一番有名な建物の内装に話が及んだときと、スタッフと同じ年頃の孫娘が可愛いと言ったとき。買ったばかりの小さなラジカセからは、田端義夫の「大利根月夜」と「十九の春」が交互に流れていた。
また冬がくる。あれから1年。夏には、冷たいお茶やコーヒーを差し入れてくれる人がいた。毎朝、散歩の途中話しに来る一人暮らしの男性もいる。周りで働く人たちとも世間話をするようになった。
「嫌なことは稀ですよ。言葉をかけてくれる人がいると、気持ちが救われますね」
雨降りの日曜日から一週間、あの3時間1冊も売れなかった時間帯に差しかかった。でも、今日は秋晴れ。昔取った杵柄で手づくりした移動式の折り畳みバックナンバー展示・収納ケースを前に、宮川さんは、しゃんとしてビッグイシューを売る。
※掲載内容は取材当時のもののため、現在と異なる場合があります。
この記事が掲載されている BIG ISSUE

17 号(2004/11/15発売) SOLD OUT
特集さようなら石油経済、こんにちは水素経済― 燃料電池と再生可能エネルギー


